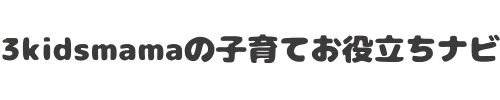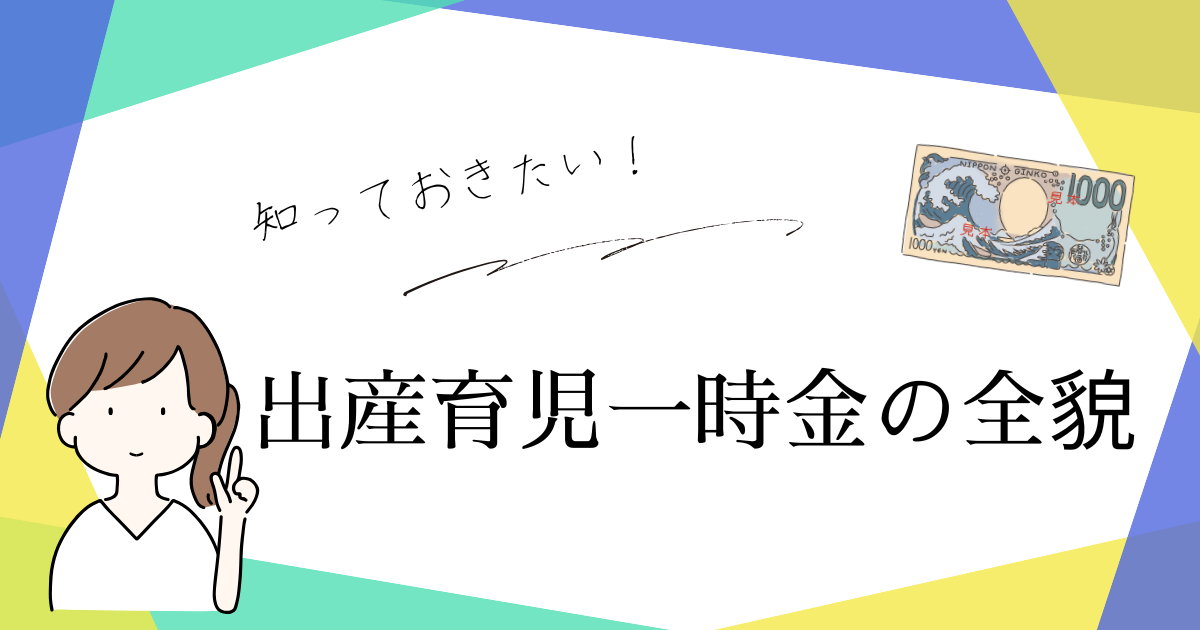出産にはお金がかかる…でも安心!
赤ちゃんの誕生は喜ばしいものですが、それに伴う出費に不安を感じる方も多いのではないでしょうか?
そんなときに知っておきたいのが「出産育児一時金」という制度です。
この記事では、制度の基本から受け取り方まで、分かりやすく解説します。
出産育児一時金とは?
出産育児一時金とは、健康保険や国民健康保険に加入している方(またはその被扶養者)が出産した際に支給されるお金のことです。
出産費用の負担を軽減するために設けられた制度で、赤ちゃん一人につき50万円が支給されます(2023年4月以降の出産の場合)。
支給額の詳細
| 出産の状況 | 支給額 |
|---|---|
| 産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降の出産 | 50万円 |
| 上記以外の医療機関、または妊娠22週未満の出産 | 48.8万円 |
受け取るための条件
出産育児一時金を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。
✅ 妊娠4カ月(85日)以上で出産したこと(早産・死産・流産・人工妊娠中絶を含む)
✅ 健康保険・国民健康保険に加入している、または被扶養者であること
出産育児一時金の受け取り方法
受け取り方法は3つあります。
1. 直接支払制度(最も一般的!)
📌 仕組み
[健康保険] → [医療機関へ直接支払い] → [出産費用を相殺]メリット: 事前に高額な出産費用を準備する必要がない
注意点: 利用には医療機関との合意書が必要
2. 受取代理制度
📌 仕組み
[健康保険] → [医療機関が代理で受け取る] → [出産費用に充当]一部の診療所・助産所で利用可能。
3. 出産後に申請
📌 仕組み
[自己負担で出産] → [後日、申請] → [健康保険から支給]メリット: 医療機関が対応していない場合でも受け取り可能
注意点: 申請手続きが必要で、支給まで時間がかかる
📌 申請先
- 健康保険加入者 → 協会けんぽ、健康保険組合など
- 国民健康保険加入者 → 市区町村役場
出産費用が足りない場合は?
出産費貸付制度を活用しよう!
出産育児一時金の支給前に最大40万円(8割相当)を無利子で借りられる制度があります。
📌 貸付の流れ
[申請] → [最大40万円貸付] → [出産費用に充当] → [後日、一時金が振り込まれ差額を精算]📌 対象者
- 出産予定日まで1カ月以内
- 妊娠4カ月以上で一時的な支払いが必要な方
申請は健康保険の窓口で行えます。
退職後でも受け取れる?
退職日の前日まで1年以上健康保険に加入していた方は、退職後6カ月以内の出産でも一時金を受け取ることができます。
📌 退職後の受給可否フローチャート
1年以上加入していた?
├─ はい → 6カ月以内の出産なら受給可能!
└─ いいえ → 対象外📌 資格喪失後の手続きについては、加入していた健康保険に確認が必要です。
申請方法と問い合わせ先
出産育児一時金を受け取るための申請手続きは、加入している健康保険によって異なります。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は健康保険によって異なりますが、一般的には以下のものが含まれます。
✅ 出産育児一時金支給申請書(各健康保険の指定用紙)
✅ 出産証明書(医療機関で発行)
✅ 保険証のコピー
✅ 振込先口座の情報
✅ 出産育児一時金内払金支払依頼書(該当する場合)
✅ その他、保険者が指定する書類
📌 申請先
- 協会けんぽまたは健康保険組合加入者 → 各保険者の窓口
- 国民健康保険加入者 → 市区町村役場
問い合わせ先
📞 協会けんぽ・健康保険組合の問い合わせ窓口
📞 国民健康保険の問い合わせ窓口(市区町村役場)
📞 厚生労働省保険局保険課(制度に関する問い合わせ)
申請方法や詳細な手続きは、加入している健康保険の公式サイトや窓口で確認しましょう。
まとめ
✅ 赤ちゃん1人につき50万円が支給(条件あり)
✅ **主流は「直接支払制度」**で自己負担が軽減
✅ 出産費貸付制度で事前にお金を借りることも可能
✅ 退職後の出産でも受給可能なケースあり(手続き要確認)
✅ 申請方法を確認し、必要書類を準備することが大切!
出産は喜ばしいものですが、費用面の不安も大きいですよね。
「出産育児一時金」を活用すれば、経済的負担を軽くすることができます。
事前にしっかりと情報を押さえて、安心して出産を迎えましょう!
📌 補足:出産費用は地域や医療機関によって異なります。